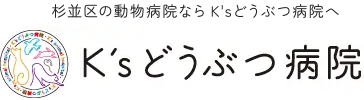歯科
口臭が強い、歯ぐきが赤い・出血する、といった症状は、歯周病や歯肉炎の可能性があります。
K’sどうぶつ病院では、歯石の付着や歯ぐきの炎症、口の痛みなどの症状についての診察を行い、必要に応じてスケーリング(歯石除去)や治療を行っています。
お気軽にご相談くださいませ。
犬、猫。フェレット、ウサギ、モルモット、ハムスター、ハリネズミ、フクロモモンガ、チンチラ、デグーなどのエキゾチックアニマル。
その他の動物についてもお気軽にご相談ください。
※爬虫類(カメ・ヘビ・トカゲなど)と鳥類の診察は行っておりません。
歯科でよく見られる症状
- 口臭が強い
- 歯石・歯垢の付着
- 歯ぐきの赤み・出血
- よだれが多い
- 食欲不振・硬いものを噛まない
- 口が痛そう・違和感があるそぶり(口をひっかく、こする、あぐあぐする)
歯科で診断される主な疾患
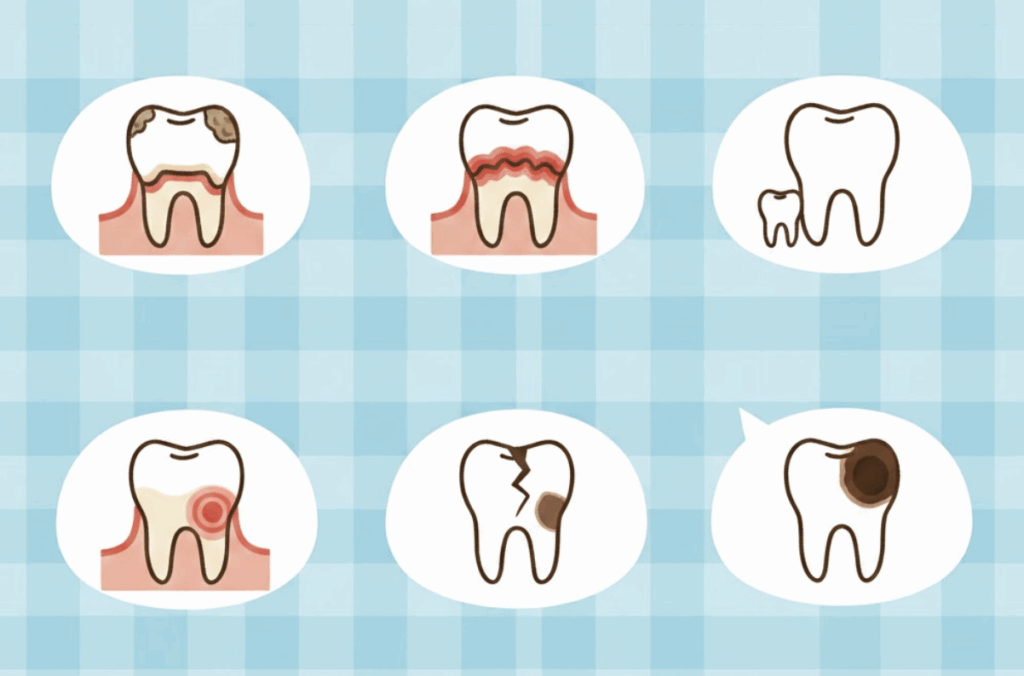
- 歯周病
- 歯肉炎
- 乳歯遺残
- 口内炎
- 歯折
- う蝕(虫歯)
歯科の診察・治療の流れ

まずはお口の状態をみながら、現在気になっている症状(口臭・歯の汚れ・食欲の変化など)をお聞きします。
初診の場合は問診票をご記入いただき、全身状態や既往歴も確認します。

診察室で獣医師が口の中を確認します。
歯石の付着、歯肉の炎症、ぐらつきの有無、口臭、痛みの反応などを丁寧にチェックします。
必要に応じて全身の健康状態(心臓・腎臓など)も確認し、麻酔を行う場合のリスクを把握します。
麻酔下での処置が想定される場合は、事前に血液検査を行い、肝臓・腎臓などの機能を確認します。

診察結果と検査内容をもとに、歯石除去(スケーリング)や抜歯が必要かなど、今後の治療方針をご説明します。
麻酔の有無・費用・所要時間・リスクなどについても、飼い主さまにしっかりとご納得いただいてから進めます。

当院では、より正確な診断のため歯科用レントゲンを導入しています。麻酔下で歯の根や骨の状態を確認し、抜歯の必要生について判断いたします。
治療は基本的に全身麻酔下で行います。
まず超音波スケーラーで歯石や歯垢を丁寧に除去し、その後ポリッシング(研磨)で歯の表面を滑らかに仕上げます。
これにより、再び歯石が付きにくい状態を保ちます。
重度の歯周病の場合は、感染した歯肉や歯を治療・抜歯することもあります。
処置後は覚醒室で安全に麻酔から目を覚ますまでしっかり見守ります。
目が覚めて安定したらお迎えとなり、処置内容や今後のケア方法をご説明します。
歯石は時間とともに再形成されるため、定期的なチェックとおうちでのケアが大切です。
歯磨きの方法、デンタルガム・フードの選び方など、予防ケアのポイントもご案内いたします。
料金表
| 術前検査(血液検査・凝固系検査) | ¥16,000 |
| スケーリング術 | ¥50,000〜¥100,000(重症度や、抜歯によって変動します) |
よくあるご質問
はい。犬猫の歯石除去(スケーリング)は基本的に全身麻酔下で行います。
麻酔をかけることで、痛みや恐怖を与えずに、歯肉の奥まで丁寧に歯石を除去できます。
無麻酔のスケーリングでは、表面の歯石しか取れず、歯周ポケット内の菌が残るため再発や炎症の原因になります。
当院では事前に血液検査や心臓のチェックを行い、麻酔リスクを評価してから実施します。
高齢の子でも全身状態が安定していれば麻酔下で安全に行えるケースが多いです。
必要に応じて麻酔量を調整し、モニタリングを行いながら慎重に処置を進めます。
一般的には3〜6か月ほどで少しずつ再形成します。
日々の歯磨きやデンタルガムなどのホームケアを続けることで、再付着を大幅に遅らせることができます。
定期的なチェックや半年に一度の歯科健診をおすすめしています。
はい。毎日の歯磨きは最も効果的な予防法です。
最初は口元に触る練習から始め、無理のない範囲で徐々に慣らしていきましょう。
歯磨きが難しい場合は、歯磨きシートやデンタルガムの併用も有効です。
歯周病が進行して歯を支える骨が溶けてしまっている場合は、抜歯が必要になることがあります。
レントゲンで根の状態を確認し、できるだけ歯を残せるよう判断いたします。
症例報告
準備中
お問い合わせ・ご予約方法
お問い合わせやご予約はLINEにて受け付けております。
お急ぎの場合や緊急の場合は、受付時間内であればお電話でもご対応がか可能です。
受付時間 9:00〜11:30/16:00〜18:30 (日・祝:9:00〜11:30)
お気軽にご連絡くださいませ。